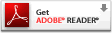出産したとき
出産した際に、健康保険組合に申請できる給付金の手続きについてまとめました。
提出期限のあるものや、証明や添付書類が必要なものもありますので、間違いのないよう気を付けて手続きを行いましょう。
赤ちゃんを扶養に入れる手続きはこちら
出産育児一時金
被保険者または被扶養者である家族の妊娠4ヵ月以上(85日)経過した出産について、1児につき『出産育児一時金』として、産科医療補償制度加算対象出産の場合には500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は、488,000円が支給されます。早産、死産、人工妊娠中絶のいずれの場合についても支給の対象となります。
なお、産科医療補償制度加入分娩機関は、財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度サイトより検索できます。
産科医療補償制度サイト:http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/
| 当健保の付加給付 | |
|---|---|
| 出産育児一時金付加金 | 1児につき 50,000円 が支給されます。 |
| 家族出産育児一時金付加金 | 1児につき 50,000円 が支給されます。 |
出産費用の窓口負担を軽減する
出産費の窓口負担を軽減するしくみとして、『直接支払制度』または『受取代理制度』が利用できます。これらの制度を利用すると、窓口での支払いが出産費用から一時金の支給金額を差し引いた額だけで済みます。なお、出産費用が支給額より少ない場合には、差額が健康保険組合から被保険者に支給されます。
| A:直接支払制度 |
分娩機関が被保険者に代わって健康保険組合に一時金の申請を行うことによって、分娩機関が健康保険組合からの一時金を受け取る制度です。 直接支払制度を利用する場合健保への手続きは不要です。 【支給までの流れ】
医療機関より法定給付分の申請があり次第、付加金を被保険者にお支払いします。 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B:受取代理制度 |
被保険者が分娩機関を受取代理人として健康保険組合に一時金を事前に申請することによって、分娩機関が健康保険組合から一時金を受け取る制度で、届出をした小規模の分娩機関などで利用できます。 受取代理制度を利用するには、事前申請が必要です。 (1)医療機関などに受取代理制度利用の同意(※1)を得る。 出産育児一時金・付加金請求書(受取代理申請用)(2)健保に医療機関が『出産育児一時金・付加金請求書(受取代理申請用)』を提出 (3)健保から医療機関などへ受取代理制度利用受付を連絡 (4)分娩後に医療機関などが健保分費用を請求 (5)健保から医療機関へ分娩費用(※2)支給
※1 『出産育児一時金・付加給付請求書(受取代理申請用)』の
※2 分娩費用が出産育児一時金・付加金の支給額を超えた場合の差額は |
||||||||||||
| C:直接支払制度・ 受取代理制度の 両方を利用せずに 分娩した場合 |
① 出産育児一時金・付加金請求書
②分娩証明(申請書に証明を受けた場合には不要) 【支給までの流れ】 (1)分娩後に上記①~④を揃えて、健保に提出する。 (2)内容を確認後、健保が事業主経由で被保険者に支給します。 |
||||||||||||
| D:海外の医療機関で 分娩した場合 |
① 出産育児一時金・付加金請求書(Cと同じ申請書)
②分娩証明(申請書に証明を受けた場合には不要) 【支給までの流れ】 (1)分娩後に上記①~④を揃えて、健保に提出する。 (2)内容を審査後、健保が事業主経由で被保険者に支給します。 |
※『領収明細書』は医療機関などにより、名称が異なりますのでご注意ください。
(例:分娩費用明細書、出産費用明細書など)
また、産科医療補償制度対象分娩で、『領収明細書』には、制度加入についての印字やスタンプ等があること。
資格喪失後の分娩の場合には、付加金の支給はありません。
法定給付上限額に満たなかった差額と付加給付金を事業主経由で支給することについて
デクセリアルズ健保では、被保険者の利便性および申請漏れによる不利益を考慮し、本人からの申請がなくても自動で法定給付上限額に満たなかった差額および付加給付金を事業主経由で支給します。
被保険者が出産したとき
出産手当金
出産のため仕事を休み、その期間給料が支払われないときには『出産手当金』が支給されます。支給期間は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までを期限とした休んだ日数分です。
| 受給額 |
出産手当金(法定給付)受給期間の範囲内で会社を休んだ1日につき、手当金の「支給を始める日」以前12ヵ月間の標準報酬月額の平均額の1/30(標準報酬日額)の2/3相当額 また被保険者期間が1年に満たない場合は、以下の①か②のいずれか低い方の ①直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の1/30 ②支給開始日の属する年度の前年度の9月30日時点の全被保険者の標準報酬月額の平均額の1/30 出産手当金付加金(付加給付)受給期間の範囲内で会社を休んだ1日につき標準報酬日額の85%から法定給付を控除した額 |
|---|---|
| 提出書類 |
出産手当金・出産手当付加金請求書【手続きの流れ】 (1)ペイロールより書類が届く。 (2)案内に従い手続きを行う。 (3)社労士が内容精査し、健保へ申請書類 作成・送付。 ※但し、会社休業中に給与が支払われ、出産手当金+出産手当金付加金より給与が多い場合には支給されません。少ない場合には、その差額を支給します。 |
| 留意事項 |
産前休暇前に傷病により傷病手当金を支給されている方が、産前休暇に入り出産手当金と傷病手当金を同時に受けられるようになった時は、出産手当金の支給が優先されます。 出産手当金の支給期間中は、傷病手当金は支給されません。ただし、受給額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。 |
産前産後および育児休業中の保険料についてはこちら