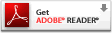医療費が高額になったとき
高額療養費の制度と手続きをまとめました。
提出期限や、添付書類が必要なものもありますので、間違いがないよう気をつけて手続きを行いましょう。
高額療養費とは
高額療養費
被保険者は医療費の一部(3割など)を自己負担していますがこの自己負担額が一定の額(自己負担限度額)を超えた時には、超えて支払った分は後から『高額療養費』として健康保険組合から払い戻されます。被扶養者についても被保険者の場合と同じ扱いです。
多数該当
高額療養費の支給が直近12ヵ月に3ヵ月以上ある時は、4ヵ月目からは限度額が下がり、家計負担を軽減します。
合算高額療養費
同一世帯で1ヵ月の医療費支払いが21,000円を超えるものが2件以上生じた時は、
合算して下表内の自己負担限度額を超えた金額が払い戻されます。
この場合、高齢受給者70歳~74歳のいる世帯では、計算方法が異なります。
この高額療養費は、通常いったん医療機関等の窓口で支払いを行い、後日払い戻されます。
なお、これらの処理は自動で行うため、原則として手続きは必要ありません。
負担の上限額は、年齢や所得により異なります。
70歳未満の方の医療費の自己負担額(1ヵ月当たり)
| 区分 | 所得区分 | 入院・外来 |
|---|---|---|
| ア | 標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【140,100円】※ |
| イ | 標準報酬月額53万円~79万円 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【93,000円】※ |
| ウ | 標準報酬月額28万円~50万円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【44,400円】※ |
| エ | 標準報酬月額26万円以下 | 57,600円 【44,400円】※ |
| オ | 低所得者(住民税非課税) | 35,400円 【24,600円】※ |
※【 】の額は4回目以降の限度額
70歳~74歳の人の医療費の自己負担限度額(1ヵ月当たり)
| 所得区分 | 高齢受給者証 の負担割合 |
外来・個人ごと | 外来・入院世帯ごと |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者III (標準報酬月額83万円以上) |
3割 | 252,600円+ (医療費-842,000円)×1% 【140,100円】※ |
|
| 現役並み所得者II (標準報酬月額53万~79万円) |
167,400円+ (医療費-558,000円)×1% 【93,000円】※ |
||
| 現役並み所得者I (標準報酬月額28万~50万円) |
80,100円+ (医療費-267,000円)×1% 【44,400円】※ |
||
| 一般所得者 (標準報酬月額26万円以下) |
2割 | 18,000円 | 57,600円 【44,400円】※ |
| 低所得者II (被保険者が市区町村民税 の非課税者等) |
8,000円 | 24,600円 | |
| 低所得者I (被保険者およびその被扶養者 全員が市町村民税非課税で、 所得が一定基準{年金収入 80万円以下等}を満たす方等) |
15,000円 | ||
※【 】の額は4回目以降の限度額
-
高額な医療費が発生する場合、自己負担限度額までの負担とするためには、「一般」と「現役並み所得Ⅲ」の区分以外の方は、資格確認書が交付されている場合、「高齢受給者証」に加えて「限度額適用認定証」を保険医療機関窓口に提出する必要があります。
(所得区分が一般、現役並みⅢの方は、限度額適用認定証は発行されません。) - 被保険者が70歳未満で被扶養者が高齢受給者の場合、市町村民税非課税世帯は低所得者I・II、それ以外の方は一般所得者の区分と同じ限度額となります。
高額療養費「限度額適用認定証」の交付について
70歳未満の方で、マイナ保険証等を提示せずに高額療養費に該当する場合は、事前に健康保険組合に申請し、自己負担限度額に関わる『健康保険限度額適用認定証』を交付されていれば、医療機関の窓口で支払う一部負担金が、自己負担限度額までにとどめることができます。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請方法
| 対象者 | 被保険者及び被扶養者 |
|---|---|
| 提出書類 |
限度額適用認定証交付申請書注意事項:有効期限は申請書を健保で受付した月から1年です。 有効期限が過ぎたとき、被保険者(被扶養者)資格を喪失した場合は、限度額適用認定証を速やかに返却してください。 ただし、被保険者の住民税が非課税の場合には、下記の「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」を提出してください。 |
| 対象者 | 被保険者の住民税が非課税の場合 |
| 提出書類 |
限度額適用・標準負担額減額認定申請書添付書類被保険者の住民税の非課税証明書(申請する時点で最新の年度) |
| 提出先 | デクセリアルズ健康保険組合 |
デクセリアルズ健保の付加給付(一部負担還元金・家族療養付加金)について
個人単位で、月毎、入院・外来別、診療科別(ただし、医療機関の処方に基づき調剤された薬代は、医療機関の自己負担額に含める)に20,000円を超えた場合に、差額が支給されます。
給付金を受取る手続きは原則として不要(自動給付)です。
ただし、100円未満の端数は切り捨てられます。
付加給付金の計算方法について
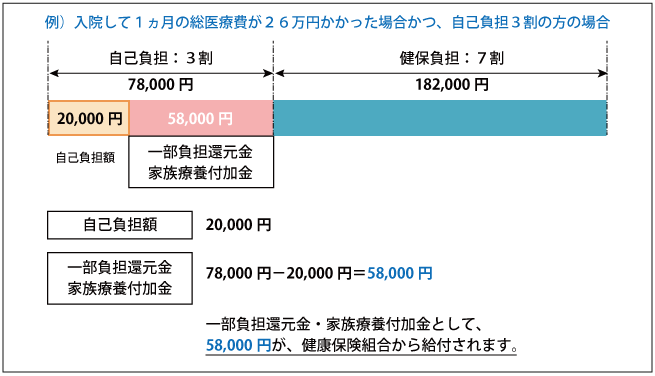
当健保では、医療費の自己負担額に対して、一部負担還元金・家族療養付加金を自動給付する制度がありますが、自治体(都道府県や市区町村)でも、乳幼児(小児)の方を対象に、医療費の自己負担分を助成する「医療費助成制度」を実施している場合があります。
健保では、自治体の助成と健保の給付金の二重給付を防ぐ為、6歳未満の方への家族療養付加金は、自動給付をしておりません。
なお、自治体からの助成が受けられない場合には、健保までご連絡ください。
特定疾病患者への負担軽減について
血友病、血液凝固因子製剤によるHIV感染症および人工透析を必要とする慢性腎臓疾患の長期患者は自己負担限度額が下記の通りになります。
ただし、院外処方(調剤薬局)での自己負担額については、下記の限度額には含まれません。
|
70歳未満の人工透析を必要とする 慢性腎臓疾患者で、上位所得者 (標準報酬月額53万円以上の方) |
20,000円 |
|---|---|
| その他の方 | 10,000円 |
なお、この給付を受けるためには、資格確認書が交付されている場合、あらかじめデクセリアルズ健保から「特定疾病認定」の交付を受けて、資格確認書と共に医療機関の窓口に提示する必要がありますので、該当される方は、交付申請を行ってください。(なお、交付申請手続きの詳細については、健保までお問い合わせください。)